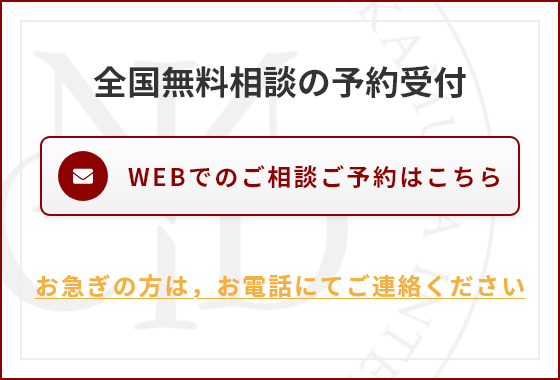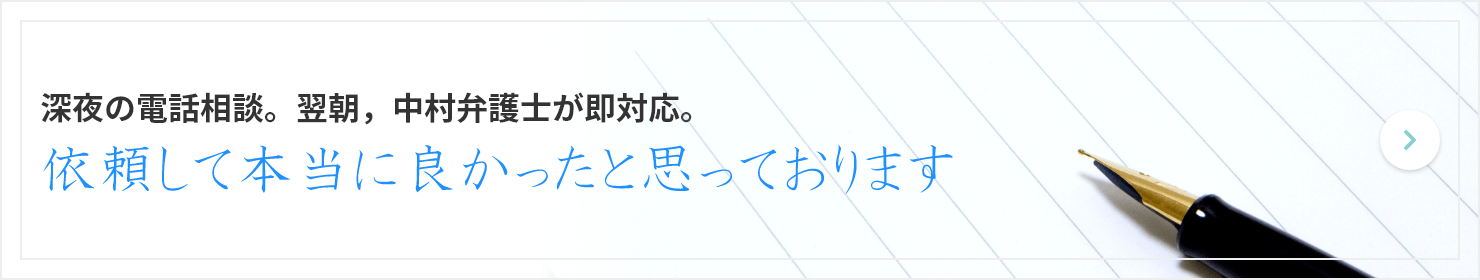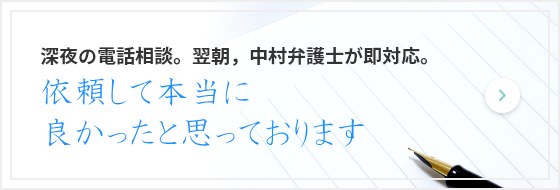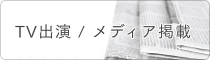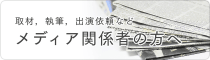独話形式の供述調書
検事に任官して東京地検に新任検事として赴任し、検察官生活がスタートした。1ヶ月ほど座学の研修があり、副部長をはじめとして先輩大検事の手柄話を散々聞かされた。その後、ようやく実務がスタートし、1ヶ月の捜査実務研修が4班に分かれて行われ、身柄事件の配点がはじまる。指導検事は、特捜部のエース級の検事で、迫力があるが人格者だった。
最初に配点された事件はシンナーの事件、毒劇物取締法違反の認め事件だった。修習生と違って今度は自分が主任検事である。午前10時前ころに事件記録が届き、ざっと目を通す。立会事務官に身柄をあげるよう指示する。「身柄をあげる」とは、検察庁建物の地下にある仮監(待機のための拘禁部屋)にいる被疑者を検事室に呼ぶことを言う。留置係の警察官に伴われて被疑者が部屋に入る。手錠に腰紐の被疑者と目が合う。私は警察官に手錠を外すようにいい、両手が自由になった被疑者は前机を挟んだ対面のパイプ椅子に座る。腰紐はつけたままで、紐の片方がパイプ椅子に縛られる。
私は黙秘権、弁護人選任権を説明した上で弁解録取手続きに入る。弁解録取は弁解を聞くだけなので黙秘権告知は法律で必須とされてはいないが、弁解を聞きっぱなしではなく、ところどころ確認することもあって取調べ的要素もあるので黙秘権を告知していた。
被疑事実を読み上げ、事実関係でどこか間違いがないか尋ねると、「その通り間違いありません。」と答え、そのとおり弁解録取書に記載して、読み聞かせ手続をし、内容を確認の上署名指印をしてもらった。弁解録取書も供述調書もそうであるが、書面作成はいわゆる口授で事務官に話して聞かせて事務官に調書を作成してもらうという方式である。検察修習で既に経験して慣れていたので問題はなかったが、修習生の頃は口授しているうち、長々と一文が続き、主語が分からなくなって、トンチンカンな文章になり、初めからやり直すというけとがしばしばで、よく被疑者に苦笑された。
口授形式の供述調書作成は日本伝統の司法慣習である。供述調書は検事が作成するが、記載された物語は検事が主語ではなく、被疑者が主語である。「私(検事)が被疑者にシンナーを吸い、残りのシンナーの瓶を持っていたのは間違いないかと聞いたところ、彼は(被疑者は)間違いないと言った。」と記載して作成するのではなく、「私は(被疑者は)昨日、路上で友達と一緒にシンナーを吸い、ラリっていたところ、警察官に職務質問され、持っていたシンナー入り小瓶も見つかっちゃいました。」という、被疑者の独話形式で作成される。つまり、検事が被疑者に代わって調書を書いてあげている、「なりすまし調書」ということになる!ただ、オレオレ詐欺のなりすましと異なるのは、調書の末尾で突然検事が現れて、「以上の通り録取の上、被疑者に読み聞かせたところ、間違いがない旨申し立て本調書末尾に署名指印した。」という文章が入ることである。なんだ、検事かよ、と言った感じである。
これは江戸時代、いやもっと昔からの日本のお裁きの慣習であったらしい。文盲の百姓、庶民に代わって町奉行の吟味方が取調べ帳に筆でスラスラと書く(私が検事成り立ての頃もパソコン調書ではなく、手書き調書だった)。その時、吟味方や町奉行が自分で書くのでなく、百姓の言わんとするところを整然とした文章で助手の下役人に口授し、それを下役人が書き取るのである。皆さんも大岡越前のテレビドラマで加藤剛がやっていたのを覚えていると思う。明治になって近代司法が導入された後もそう簡単には慣習は変えられず今に至るまでこの被疑者独話形式、口授形式がとられている。
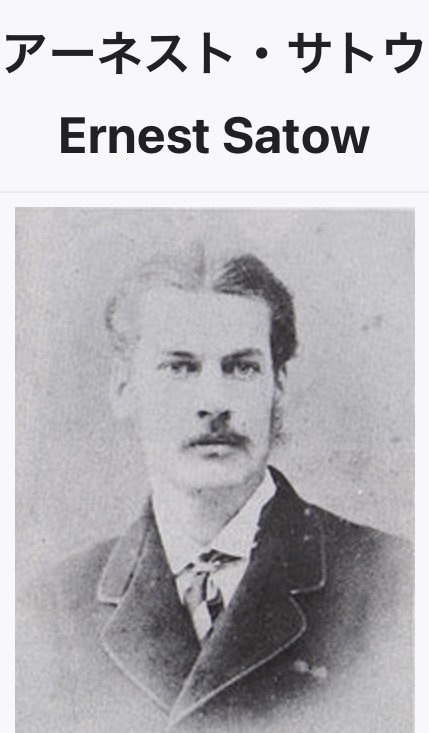 明治維新後に駐日イギリス公使として赴任したアーネストサトーは、この口授を目にして「イギリスの裁判官のsumming up(説示)みたいだ。」と、その著書「一外交官の見た明治維新」で書いている。イギリスでは、法律の素人の陪審員に対し、有罪無罪の評決前に、審理で明らかにされた事件の要点を口頭で説明する手続きがある。それに似ているというのだ。まんざら前近代的なシステムでもないらしい。しかし、この日本の独話形式の供述調書作成は、密室で行われるため、いわゆる「検事の作文」疑念から数多くの冤罪事件が生まれた。何事も密室は良くないのである。
明治維新後に駐日イギリス公使として赴任したアーネストサトーは、この口授を目にして「イギリスの裁判官のsumming up(説示)みたいだ。」と、その著書「一外交官の見た明治維新」で書いている。イギリスでは、法律の素人の陪審員に対し、有罪無罪の評決前に、審理で明らかにされた事件の要点を口頭で説明する手続きがある。それに似ているというのだ。まんざら前近代的なシステムでもないらしい。しかし、この日本の独話形式の供述調書作成は、密室で行われるため、いわゆる「検事の作文」疑念から数多くの冤罪事件が生まれた。何事も密室は良くないのである。