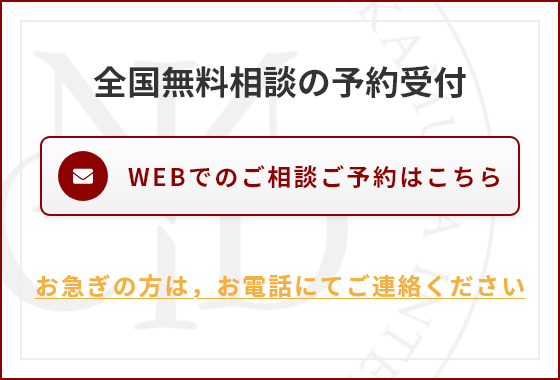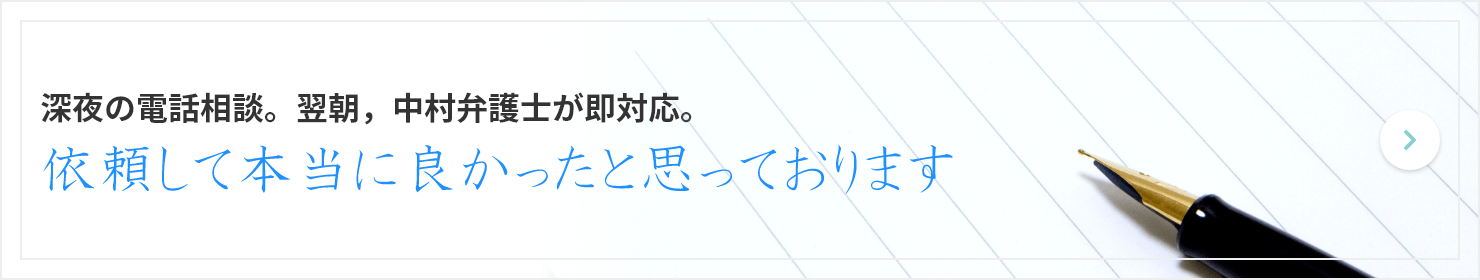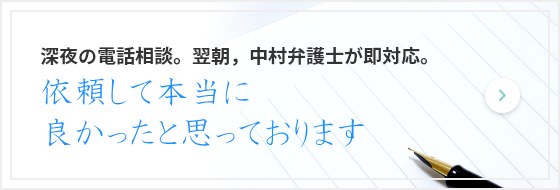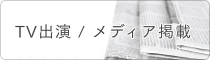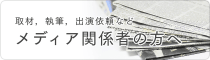刑事弁護士の中の「有罪推定」意識について
足利事件の菅家利和さんが書いた「冤罪 ある日私は犯人にされた」(朝日新聞出版社)を読みました。
この事件は,菅家さんが捜査段階のみならずどうして公判でも最初は犯行を認めていたのか,関心があったので,買って読んでみました。
一審で担当した弁護士は国選ではなく,私選だったのですね。しかも,捜査段階の当初から選任されていて,公判では二人の弁護士が担当している。どうして菅家さんは弁護士に自分が無実であることを打ち明けなかったのか不思議だったのですが,この本を読んで,「弁護士が偉そうにしている。」「警察,検事,弁護士の区別がつかなかった」という記述を読んで考えさせられてしまいました。
弁護士もDNAのマジックにかかっていたのでしょうか。DNA結果が一致してるのだから犯人に間違いがないというマジックにかかっていたのでしょうね。
裁判官は「無罪推定」の心証で審理に臨まなければいけないとはよく言われますが,実は,刑事弁護士にも「有罪推定」で依頼者と向き合ってしまうという落とし穴があるのかもしれません。
この「DNA」の問題は冤罪の象徴のような気がします。菅家さんの事件ではDNA結果が警察,検事,弁護士,裁判官に予断,偏見,思い込みを与えてしまいましたが,ある事件では,被疑者・被告人の「前科」がこのDNAの役割を果たすかもしれません。同種前科があるから今回の事件もあいつが犯人だという偏見です。また,ある事件では,出自がDNAの役割をはたすかもしれません。こうしたDNAマジックは冤罪を生む仕掛けとしてどこにでも潜んでいるということを肝に銘じなければなりません。
その点で,ちょっと気になることがあります。このブログでも触れましたが,「米原タンク殺人」です。全面否認のまま起訴されたのですね。これは裁判員裁判対象事件であり,現在,公判前整理手続が行われているはずです。まさか冤罪ではないでしょうね。