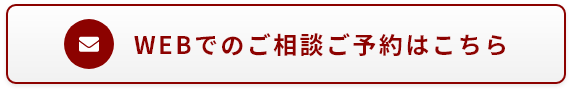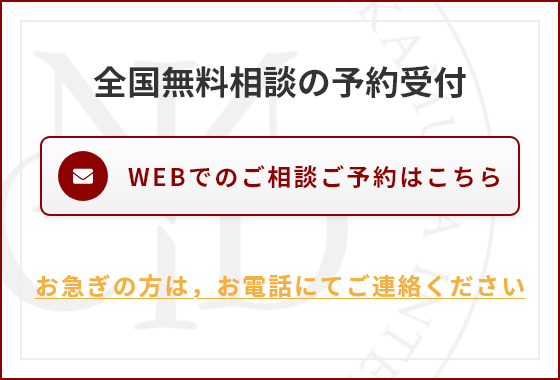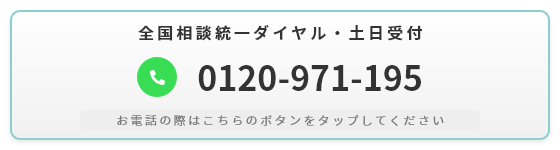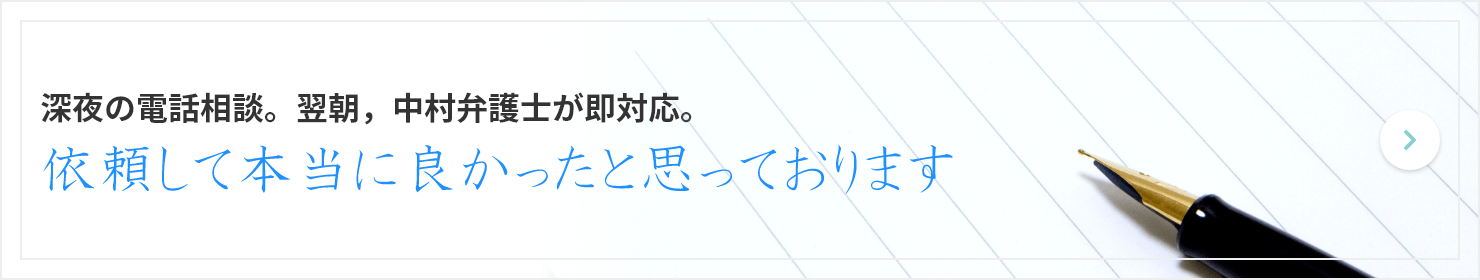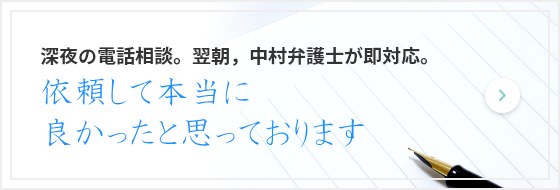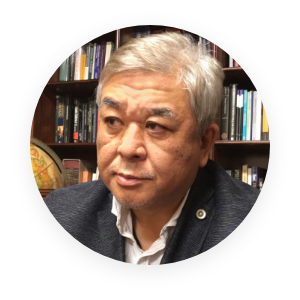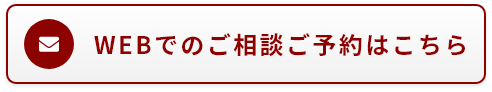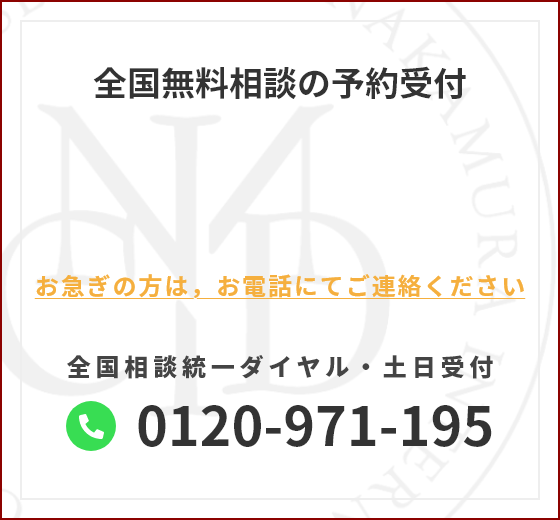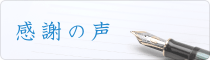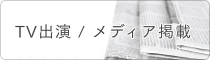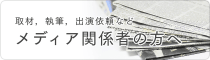勾留実務は最高裁決定で変わるか
今日は,「勾留請求の却下と裁判所の姿勢」に関する注目記事です。
逮捕した容疑者について検察が身柄拘束の継続を求める「勾留請求」を裁判所が認めない割合が年々増えている。10年前まで1千件に1件程度だったが、2010年に100件に1件を超え、13年まで上昇傾向が続く。最高裁も拘束を許可しない判断を相次いで示すなど、裁判所が「人質司法」を見直す姿勢を鮮明にした形。専門家は「市民が参加する裁判員裁判の時代に適合している」と評価する。(2014年12月4日1時30分 日本経済新聞)
警察が被疑者を逮捕した場合,逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません(刑事訴訟法203条1項)。検察官は,被疑者の弁解を聞き,更に被疑者の留置の必要があると判断したときは,24時間以内に,裁判官に勾留請求をしなければなりません(刑事訴訟法205条1項)。そして,裁判官が検察官の勾留請求を認めれば,10日間(勾留延長があれば最大20日間),被疑者を勾留することができます(刑事訴訟法207条1項本文)。
刑事訴訟法が勾留という被疑者の身柄拘束制度を定めたのは,検察官が被疑者を起訴するか否かを決める権限を持っている(刑事訴訟法247条,248条)ことから,検察官に被疑者の身柄を拘束させたまま,起訴・不起訴の判断をするための必要な捜査を行うことを認めているからです。勾留の要件には①住居不定であること,または②罪証隠滅のおそれがあること,または③逃亡のおそれがあること(刑事訴訟法207条1項,60条1項各号)がありますが,被疑者が逃亡してしまえば取調べはできませんし,被疑者が罪証隠滅をしてしまっても,適切な捜査ができないことになるので,このような危険がある場合には,被疑者の身柄を拘束して捜査することを許容したのです。
被疑者を勾留した場合,20日間という期間制限はあるものの,検察は警察への電話1本で被疑者を検察庁まで連れてきてもらって取調べを行うことができ,警察も被疑者の身柄を用いて,実況見分などを行うことができるので,捜査機関にとって,捜査がしやすいのです。
他方,被疑者は,警察の留置施設などに連日勾留され,検察庁で検察官の取調べを待つ間は,同行室と呼ばれる場所で,他の被疑者と一緒に,手錠を付けられたまま木の椅子などに一日中座って待たなければなりません。ほとんどの被疑者が捜査機関による捜査を受けた経験も,留置施設に入れられた経験も,手錠をつけられたまま過ごす経験もしたことがありませんから,その肉体的・精神的苦痛は甚大です。
このような捜査機関によるプレッシャーを絶えず被疑者は受けることになるので,勾留が長期化すると,被疑者は,意に沿わない自白や,検察や警察の意に沿った供述をしてしまうこともあるのです。このような実態が「人質司法」と呼ばれるもので,冤罪の温床となっていると批判される理由です。
今回,取り上げたいのは,このような人質司法を改め,検察の勾留請求を容易には認めない姿勢を裁判所が打ち出していることです。以前は,検察官の勾留請求に対して,原則として,特別な理由がない限り勾留請求を却下しない,とする姿勢もあったように思います。しかし,今,その変革期にあるといえます。この裁判所の変化は,実は,被疑者国選で就いた弁護士や刑事専門の私選弁護士の努力なくして生まれませんでした。被疑者本人からの接見要請や家族からの相談等によって直ちに被疑者に接見し,事案の性質,認否,生活環境等を聞き,事件に即した身柄解放活動に従事します。家族から身柄引受書をとったり,犯行現場等に近づかないことを担保する方策を練ったりして,裁判官が,検察官の勾留請求を却下しやすい環境を弁護士がお膳立てしてあげるのです。
このような弁護士の努力に言及していない今回の記事には大いなる不満がありますが(笑),いずれにしてもただでさえ身柄拘束期間が長いと先進国から指摘され,「人質司法」と揶揄されてきた我が国刑事司法制度にとって,勾留請求却下率が高くなったというのは喜ばしいことです。
今回取り上げた最高裁の決定(最高裁第1小法廷平成26年11月17日決定)は,逃亡のおそれ等は認められない事案でしたので,主に罪証隠滅のおそれに言及しています。注目すべきは,「罪証隠滅の現実的可能性がどの程度あるかが問題」とし,その「可能性が高いことを示す事情」の立証を検察官に求め,今回はそれがないとして,勾留請求を認めなかったのです。本件は,通勤通学の電車内での痴漢事件だったため,被疑者と痴漢被害者は見ず知らずの関係で,被疑者が被害者に接触することは容易ではなかったのでしょう。一般的に,被疑者が痴漢被害者に対して働きかけをし,供述の変更を迫ったり,被害届を取り下げさせたりするなどして,自らの罪を免れようとする危険は,抽象的には存在します。しかし,その具体的可能性の立証までなければ,勾留の要件としての罪証隠滅のおそれは認めない,と判断したのです。
最高裁の判断は,個々の裁判官や裁判体,ひいては検察官にも影響を与えることでしょう。今後,この最高裁の判断を前提として,人質司法の運用がどのように変わっていくのか,注目です。このような傾向が,勾留実務のみならず,保釈実務においても波及していくことを期待し,刑事弁護士として,一層の努力をしていきたいです。